教員採用試験の面接。
あなたが話す内容がどれだけ素晴らしくても──
「聞き取りづらい」と思われたら、それだけで評価は下がる。
なぜか?
教員は「伝える」仕事だからだ。
子どもにも、保護者にも、同僚にも、
わかりやすく、はっきり届けられる力が求められている。
だから面接官は、あなたの言葉の「中身」だけじゃない。
「届け方」も、しっかり見ている。
では、どうするか。
まず、答えは“結論から”。
どんな質問にも、まず一言で答える。
たとえば、
「なぜ教員を志望したのですか?」
→「私は、すべての子どもの可能性を信じたいと思い、教員を志望しました。」
これだけで、面接官の頭にすっと入る。
そのあと、具体例やエピソードを加えればいい。
次に、「ひと呼吸おきながら話す」。
一文一文、間をとって話す。
間があると、面接官は情報を整理できる。
間がないと、情報が渋滞して、聞く側にストレスを与えてしまう。
さらに、「構造をつけて話す」。
話すときは、シンプルな型を意識する。
「結論 → 理由 → 具体例 → まとめ」
この順番を守るだけで、話がすっきり伝わる。
たとえばこんな感じ。
結論:「私はチームワークを大切にしています。」
理由:「学校現場は一人では成り立たないと考えるからです。」
具体例:「実際に大学時代、教育実習で〇〇の活動に取り組みました。」
まとめ:「だから、教員になってからも協力し合う姿勢を大切にします。」
こう話せるだけで、「聞きやすいな」と思わせられる。
そして、「言葉を選びすぎない」ことも大事だ。
完璧な表現を探して口ごもると、リズムが崩れる。
大切なのは、「伝わる」こと。
多少シンプルでも、自分の言葉で、堂々と言い切ろう。
声も大切だ。
大きすぎず、小さすぎず。
はっきりと、前へ押し出すように話す。
緊張で声が震えそうなら、面接室に入る直前に腹式呼吸。
「私は伝えにきたんだ」と、自分に言い聞かせる。
聞き取りやすい話し方は、才能じゃない。
意識と練習で、誰でも身につく。
最後に、こう考えよう。
「どう話すか」は、「どう相手を思いやるか」だ。
面接官に「伝わりやすく届ける」。
それは、子どもたちにも「わかりやすく教える」ことにつながっていく。
聞き取りやすい人になること。
それは、未来の先生としての第一歩だ。

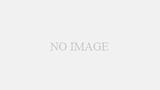
コメント